ヴィパッサナー
サヤジ・ウ・バ・キンの伝統のもと
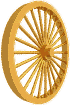
瞑想
S.N.ゴエンカの指導による
ヴィパッサナーの指導者たち
サヤ・テッジ
1873-1945
次の記事は、ミャンマーのダンマーチャリヤ(法主、法を説き教える人)ウ・フテェイ・フラインの「サヤ・テッジ」をもとにしている。
サヤ・テッジ(ミャンマー語で、サ・ヤ・タ・ジと発音される)は、1873年6月27日に、ラングーン川の対岸にあり、ラングーンから南へ約13キロメートルの所にあるピョウペイジという農村に生まれた。幼少の名前は、マウン・ポ・テッという。 父親は、マウン・ポ・テッが十歳のときに亡くなった。そこで、母親がひとりで、ポ・テッおよびポ・テッの弟二人と妹一人の四人の子どもの面倒を見なければならなくなった。
母親は、村でフリッター(野菜の揚げたもの)を売って生計を立てた。そして、まだ少年のポ・テッが、売れ残ったフリッターを売り歩く役をおおせつかった。しかし、しばしば一つも売ることができずに帰ってきた。彼は、あまりにも内気で、声を出してものを売ることなど、とてもできなかったのである。そこで、母親は二人の子どもを歩かせることにした。ポ・テッがフリッターを入れた器を頭に乗せて運ぶ役、そして、彼の妹が売り子の役というふうに。
家族のために働かなければならなかったので、ポ・テッは六年しか学校教育を受けることができなかった。彼の両親は土地も水田も持っていなかったので、収穫期になると、他の人の水田で収穫後の残りの稲の茎を拾い集めたものだった。ある日のことだった。水田からの帰り道で、ポ・テッは乾ききった池で死にそうになっている小さな魚を数匹見かけた。彼は魚を捕まえて、家に連れて帰った。彼の村の池に放してやろうと思ったのである。ところが、彼の心の内を知らない母親は、彼を叱った。彼は説明した。すると、彼女は言った。「サードゥ!サードゥ!(よくやった、よくやった)」彼女はやさしい母親で、けっして叱るということがなかったが、アクサラ(不善、悪い行い)については厳しかったのである。
十四歳になると、マウン・ポ・テッは米を運搬する牛車の御者として働きはじめた。そして、日々の稼ぎを母親に渡した。そのころは彼はまだ小さかったので、牛車の乗り降りに踏台として木箱を使わなければならなかった。
ポ・テッの次の仕事は、サンパン船の漕ぎ手だった。ピョウペイジ村は平らな耕作地にあった。そして、川がたくさん流れていて、すべてラングーン河に注ぎ込んでいた。いったん洪水が起こると、大変だった。そんなときには、移動のためにこの長くて、底の平らなサンパン船が頼りになるのである。
ある精米所の主人は、小さなポ・テッが一所懸命働くのを見ていた。そして、彼を雇うことにした。賃金は、一月六ルピー(約三十円)だった。ポ・テッは一人で精米所に住み、食事は質素だった。米と、皮を剥いて干したえんどうまめのフリッターを常食にした。
はじめ、彼はインド人の夜警や労働者から米を買った。彼らはポ・テッに、豚やにわとりの餌にする精米したあとの残りの米を自由にもっていってよいと言ってくれた。ポ・テッは、精米所の主人の許可も得ていないのに、勝手なことはできないと言って、それを断わった。主人はそれを知って、ポ・テッに許可を与えた。しかし、やがて間もなくポ・テッの働きぶりに感心した主人が米を与えてくれるようになったので、米を拾い集めて食べる必要もなくなった。それでも、ポ・テッは残りの米をかき集めた。そして、米も買えない貧しい村人に配った。
一年後に、彼の給料は十ルピーに上がった。二年後には、十五ルピーに上がった。やがて、彼の給料は二十五ルピーにまで上がった。彼にとっても母親にとっても、生活が楽になった。
マウン・ポ・テッは慣習に従って、十六歳で結婚した。彼の妻のマ・フムインは、裕福な米商人で地主でもあった人の三人姉妹の末っ子だった。夫婦は、一男一女の二人の子どもに恵まれた。彼はミャンマーの慣習に従って、妻の両親と共に暮らした。妻のすぐ上の姉のマ・インは独身を通し、小さな商売を行い成功していた。彼女は後に、ポ・テッの瞑想の修行実践を支えるようになる。
ミャンマーには、青少年期の一時期に見習い僧となって修行する習慣があるが、ウ・テッには、その機会がなかった。彼の甥のマウン・ニュアンが十二歳になり、見習い僧となったとき、ウ・テッにもはじめてその機会が訪れた。後になって、ある一時期、彼はビック(出家僧)となって修行する機会も与えられている。
二十三歳のころに、彼は、在家の指導者サヤ・ニュアンからアーナーパーナ瞑想の手ほどきを受けた。そして、七年間その修行を続けた。
ウ・テッ夫婦には、村に友人や親戚がたくさんいた。夫婦は、家族や 親戚、そして友人たちとともに仲良く、あい和して、理想的な生活を送っていた。
しかし、1903年に、この村をコレラが襲ったとき、その幸せはこなごなにされた。多くの村人が亡くなった。数日で亡くなった人もいたが、そのなかには、ウ・テッの息子とまだ十代の娘も含まれていた。彼らは、父親の腕の中で亡くなったという。ウ・テッの義兄弟のコ・カイエとその妻も、ウ・テッの娘の遊び友だちだった姪も亡くなった。
この災難に、よりどころを失ったウ・テッは、苦しみから抜け出す道を切に求めた。そして、不死の境地を探す旅にでる許可を、妻や義理の姉のマ・イン、その他の親戚の人々に願い出た。
ウ・ニョウを道づれにして、ウ・テッは、道を求めてミャンマー中を歩いた。山の修道場、森の僧院を訪ねて、出家者あるいは在家者を問わずに、教えを希った。最終的に、彼は、最初の先生であったサヤ・ニュアンの指示に従い、レディ・サヤドォーのもとで修行するために、北のモニワ(現地ではモンユワ)を目指した。
ウ・テッの旅の間、妻と義理の姉は、村に留まって、水田を管理した。最初の数年間は、ウ・テッは、家族の様子を見るために、定期的に村に帰った。家族に繁栄があるのを見て、安心して、彼は以前にも増して、継続して深く瞑想するようになった。彼は、レディ・サヤドォーとともに、七年間修行したが、その間、妻と義理の姉が収穫を得て、毎年彼に送金して、彼を支えた。
レディ・サヤドォーのもとで修行を終えたウ・テッは、ウ・ニョウとともに村に帰った。しかし、以前の家庭人の生活には戻らなかった。レディ・サヤドォーのもとを去るときサヤドォーに、サマーディ(心の集中力)とパンニャー(心の浄化による智恵)をさらに育むために、真剣に修行し、やがては瞑想の指導をするようにといわれてきたためである。
したがって、彼らはピョウペイジに戻ったとき、家の農園の端に建つサーラー(休憩所)へ、まっすぐに向かった。そしてそこを、瞑想ホールとして使いはじめた。近所に住むある女性に頼んで、日に二回、食事を用意してもらい、修行を続けた。
このようにして、ウ・テッは、一年間過ごし、急速な進歩を遂げた。その修行期間を終えるにあたって、彼は先生の指導を仰ぎたく感じた。レディ・サヤドォー先生には直に話すことはできないけれども、先生の本は家の戸棚の中にあったので、彼は家に帰り調べることにした。
そのころ、彼の妻も姉も、それほど長いあいだ家に戻らないウ・テッに腹を立てていた。彼の妻は、別れようとさえ思っていた。だから、ウ・テッが近づいてくるのを見たとき、出迎えも挨拶もしないでおこう、と二人は決めていた。ところが、彼が戸口に立ったとき、二人とも思わず、心から迎え入れてしまった。ウ・テッは、長い無沙汰を詫びた。二人の姉妹は、それを許した。
彼女たちは、彼にお茶と食事を差し出した。そして、彼は、先生の本を調べることができた。彼は、妻に、自分は今、八つの戒律をとって暮らしているので、普通の家庭人の生活には戻れないということを、つまり、これからは兄と妹のように暮らさなければならないということを話した。
妻と義姉は、毎朝、彼を食事に招いた。そして、彼を支えることを誓った。 彼は彼女たちのやさしさに、感謝してもしきれないと思った。唯一のお返し、それはダンマをわかちあうことだった。
妻のいとこのウ・バ・ソエなど、親戚の人々が訪れては、彼と話しをして帰った。やがて、二週間が過ぎた。昼食に通うのに時間をかけすぎているようだと、彼は妻に語った。すると、妻も義姉も、昼食をサーラーまで届けようと言ってくれた。
村の人々は、はじめのうち、ウ・テッの熱意を誤解して、瞑想の指導を受けに来ようとはしなかった。失ったものへの悲しみがあまりにも深く、また、長いあいだ村を離れていたために、ウ・テッの頭がおかしくなったと、人々は考えたのである。しかし、ときとともに人々は、ウ・テッの話や行為から、彼が真に世俗を超越した人であり、ダンマとともに生きている人であることを知るようになった。
やがて、ウ・テッの親戚や友人たちが、瞑想を教えてほしいとやって来るようになった。 ウ・テッは、1914年に、十五名ほどの人にアーナーパーナ瞑想を指導した。彼が四十一歳のときであった。生徒はみんなサーラーに留まって修行したが、様子を見に家に帰る者も幾人かはいた。法話(講話)も行ったが、これは瞑想者ばかりではなく、興味のある人ならばだれでも参加することができた。そして、彼の話に耳を傾けた人はだれでも、彼の知識の広さに感嘆した。そして、ウ・テッはダンマの理論面においては暗いという人の噂を、みずから打ち消した。
妻と義姉が財政面で支えてくれたのと、他の家族の人々の助けもあって、瞑想のコースのための食事も他に必要なものもすべて賄うことができた。ときにはこんなこともあったと伝えられている。コースに参加したため労賃が得られなかった人々がいたが、そのような人に賃金を与えたと。
一年指導した後、1915年頃のことだが、ウ・テッは妻と義姉、それから家族の者を数人モニワに誘った。レディ・サヤドォーに敬意を表わすためであった。サヤドォーはそのころ、七十歳になっていた。ウ・テッが自分の瞑想の体験について、また指導したコースについて報告すると、サヤドォーはことのほか喜ばれたという。
レディ・サヤドォーがウ・テッに、彼のつえを与えたのは、ウ・テッがこうしてサヤドォーを訪ねていたときのことである。
「わが優れた弟子よ、つえを受け、道を歩み続けよ。このつえは、おまえに長生きしてほしいから渡すのではない。おまえはよくやってきた。これは、その報いである。これからも災いなく、よくやっていけるようにという願をこめて、このつえを渡そう。今日これからは、ナーマとルーパ(精神と物質についての真実を、六千名の人に説きなさい。ダンマは尽きることがない。さあ、サーサナ(ブッダの教えの時代)の時を告げなさい。その教えを広めなさい。わたしに代わって、サーサナに敬意を表わしなさい。」
翌日、レディ・サヤドォーは、彼の僧院の僧侶を一同に集めた。ウ・テッには、十日から十五日間留まって、彼らに指導してほしいと要請した。それから、サヤドォーは僧侶たちに告げた。
「みなさん、ノートをとりなさい。この在家の人は、この国の南からやって来たウ・ポ・テッさんです。わたしの優れた弟子で、わたしと同じように瞑想を指導することができます。瞑想を修行したい人は、彼について学びなさい。」それから、サヤドォーは、出家者に必要なものである食物や衣類や薬を布施して僧侶を庇護していた在家の人、ダヤカ・テッに告げた。「私に代わって、ダンマの勝利の旗を掲げなさい。」
こうして、ウ・テッは、経典に造詣の深い僧侶たち、二十五名ほどにヴィパッサナー瞑想を指導した。彼が、サヤ・テッジと呼ばれるようになったのは、このころのことである。サヤとは、先生という意味であり、ジとは、尊敬を表す接尾辞である。
サヤ・テッジは、レディ・サヤドォーが書き記した多くの書物を暗記していた。そして、経典に照らし合わせて、ダンマを説くことができた。経典に造詣の深いサヤドォーたち(僧侶の指導者、先生)も、間違いを見い出すことができなかったという。自分の代わりにヴィパッサナーを指導するようにというレディ・サヤドォーの言葉を、サヤ・テッジは厳粛に受け止めていたが、それでもやはり、理論面での知識には欠けていると思っていた。そこで、サヤ・テッジは先生に深く礼をささげて、こう述べた。
「先生の生徒のなかで、最も経典の知識に欠けているのはわたしです。ヴィパッサナー瞑想を説いてサーサナをわかちあうとおっしゃる先生のご意志は、承知しておりますが、それでも、わたしには重責です。ですから、どうか、わたしが説明を必要とするときはいつでも、わたしをお導きくださいますように。」
「けっしておまえを見捨てることはない。わたしがこの世を去るときが来ても。」そう答えて、レディ・サヤドォーはサヤ・テッジを安心させた。
サヤ・テッジとその家族は、南ミャンマーの村に帰ってきた。そして、レディ・サヤドォーから授かった任務について話しあった。サヤ・テッジはミャンマー中を歩こうと思った。そうすれば、より多くの人と接することができるだろうと思ったのである。しかし、彼の義姉は違った意見を述べた。「ここにはダンマホールがありますね。それに、私たちも、生徒さんの食事を用意したりして、お力になれると思います。ですから、ここに留まって、コースをなさってください。道を求めている人はたくさんいます。ヴィパッサナーを学びに、きっと多くの人がやって来るでしょう」 彼は、彼女の考えを受け入れた。こうして、ピョウペイジのサーラーでコースが定期的に行われるようになった。
彼の義姉が予想したとおり、多くの人が訪れはじめた。それとともにサヤ・テッジの瞑想指導者としての名声も広まっていった。彼はさまざまな人に教えた。農夫や労働者にも、また、パーリ語経典に精通した人にも。当時、ミャンマーは英国の支配下にあり、その首都はラングーンであった。そして、ピョウペイジ村は、そこから程遠くないところにあったので、ラングーンに住む人々もやって来た。政府に雇われていた人もやって来た。ウ・バ・キンもその一人であった。
次から次へと人々が瞑想を学びに訪れるようになったので、サヤ・テッジは、ウ・ニョウやウ・バ・ソエ、そしてウ・アウン・ニュアンといった瞑想経験を積んだ生徒をアシスタント指導者に任命した。
年ごとに、センターは発展していき、二百名もの生徒が集まるようになった。在家の人ばかりではなく、僧や尼僧もたずねて来た。収容しきれなくなったので、より経験を積んだ古い生徒は自分の家で瞑想し、法話(講話)のときだけ参加することにした。
レディ・サヤドォーの僧院から戻ってからは、サヤ・テッジはひとりで暮らし、食事も日に一食だけとるようになった。簡素で静かな生活であった。出家僧のように、彼はけっして、自分の修行の進歩の段階について話すことはなかった。たとえ質問されたとしても、話さなかったであろう。もちろん、生徒がどこまで達しているかなどということも。しかしながら、彼はアナーガーミ(最終解脱に至る一つ前の段階)であると、広く信じられていた。アナーガム(アナーガーミの)サヤ・テッジとして、当時知られていたのである。
当時、在家の人でヴィパッサナーを指導する人はまれであったので、サヤ・テッジは、出家僧の指導者であれば遭遇しそうもないある種の困難に直面した。たとえば、経典に精通していないという理由で、ある人々から非難されたこともある。そのようなとき、サヤ・テッジはただ、聞き流した。そして、彼ら自身が体験し、悟るのにまかせた。
三十年間、彼はみずからの経験をもとに、また、随時レディ・サヤドォーの手引き書を参照しながら、道を求めてやって来るすべての人にヴィパッサナーを指導した。1945年ころまでに、彼は、 「 数千名の人に教えなさい」という、レディ・サヤドォーから託された使命を達成したと感じた。そのとき彼は、七十二歳になっていた。妻はすでに亡く、義姉も病に冒されていた。そして、彼自身の健康も損なわれつつあった。そこで、彼は、瞑想施設を維持するために水田を202平方キロメートルほど残し、あとの富はすべて、甥や姪たちにわけ与えた。
彼の所には二十頭の水牛がいた。長年、水田をよく耕してくれた水牛であった。彼は、やさしく扱ってくれるだろうと思われる人々にこの水牛を託すことにした。こう祈りをこめて。「これまで長い間、わたしの生活を支えてくれて、ほんとうにありがとう。米も実り、たっぷり収穫することができた。これからは、おまえたちは自由の身だ。おまえたちがこのような束縛の生まれから解放されて、よりよい所に生まれることができるように。幸せであれ!」
サヤ・テッジはラングーンに移った。身体の治療のためでもあり、また、そこに住む生徒に会うためでもあった。彼は、幾人かの生徒に、自分はラングーンで亡くなるであろうと告げた。火葬は、今まで一度も行われたことのない場所で行ってほしい。そして、自分はまだすべての汚れから解放されてはいないから、つまり、アラハン(阿羅漢、心の汚れをすべて滅し去り、完璧な悟りに至った人)にはなっていないから、灰は、聖なる場所に保管しないようにと語った。
シュウェダゴン・パゴダの北側のアルツァニゴネには、彼の生徒の一人が作った瞑想センターがあった。その近くには、第二次世界大戦のときに作られた防空ごうがあった。サヤ・テッジは、そこで瞑想した。夜は、彼のアシスタント指導者の一人のもとで過ごした。会計局局長のウ・バ・キン、所得税局長官のウ・サン・テインなど、ラングーンに住む生徒たちが、熱心に訪れた。
彼は、訪ねて来る生徒の一人一人に、次のように語った。「怠らず、懸命に修行するように。瞑想の修行に訪れる僧や尼僧に、敬意を持って接するように。身体において、また、言葉や心の行為において慎み深くあるように。いかなる行為の後でも、ブッダへ敬意を表わすことを忘れないように。」
サヤ・テッジは、夕方になるとシュウェダゴン・パゴダへ通うようになった。一週間ほど経た後、風邪を引き熱を出した。同穴で坐っていたせいであった。医者の手当を受けたにもかかわらず、様態は悪くなっていった。彼の甥や姪が、ピョウペイジから見舞いに駆けつけた。毎晩、彼の生徒が五十名ほど集まって、ともに坐った。このグループ瞑想の間、サヤ・テッジは一言も語らなかった。ただ、静かに瞑想していた。
ある晩十時ころのことであった。生徒が大勢集まっていた。(ウ・バ・キンの姿はなかったが。)サヤ・テッジは仰向けに横になっていた。彼の息使いが大きく、そして長くなった。二人の生徒が見守っていた。あとの生徒は、静かに瞑想していた。十一時ちょうど、彼の息はより深くなった。吸う息、吐く息のそれぞれが、五分ほどもかかっているかのようであった。この種の呼吸が三回続いた。そして、呼吸は完全に止まった。サヤ・テッジはこの世を去った。
彼の身体は、シュウェダゴン・パゴダの北側の斜面で、荼毘に付された。のちに、サヤジ・ウ・バ・キンと彼の弟子たちが、そこに小さなパゴダ(塔)を立てた。 「社会のあるゆる階層の人々にダンマを広めよ」というレディ・サヤドォーから託された任務を成し遂げたサヤ・テッジであったが、それが、彼亡き後もこうして続いているということが、このダンマの指導者への何よりの追悼となるのではないであろうか。
